表具師店長の日記
珍しい(?)お仕事 第1弾 『 腰張り 』
表具師のお仕事は、「襖の新調・張り替え」「 障子の張り替え」「掛軸・屏風・額・衝立の表装(修理含む)」 などが
主なものですが、それ以外にも和室の内装関係で色々あります (^^)v
最近 珍しい(?) お仕事を続けてしましたので紹介しますね (^^)/
まず 第1弾は『 腰張り 』 です。
腰張りは、お茶室の内部の壁の下の方に 白や紺の紙が張っているのを見たことが無いでしょうか?
これが腰張りです (^^♪
土壁がこすれて ポロポロと砂が落ちないようにする為 張ることが多いです。
小間のお茶室の客付の壁は2段張り(約55cm)と大体決まっています。
これは着物の帯が擦れても壁が傷まないようにです。
今回した 『 腰張り 』 は お寿司屋さんの宴会場の腰張りの張り替えです !
元々は、下の写真のような からし色の紙を張ってありましたが、めくれて来たから張り替えて欲しいとの依頼でした!
 |
 |
|
| 【 貰った写真を見ると めくれあがっているのが良くわかりました 】 | ||
でも、現場に行って確認すると、紙だけがめくれているのでは無く 壁までひびが入り浮き上がっていました (@_@;)
これでは 張ることは出来ません・・・
左官屋さんにお願いし、ひびが入っている部分をめくり上げ、その部分にセメントを詰めてもらいました (^^)v
 |
 |
|
| 【 セメントを入れた状態 】 | ||
 |
 |
|
| 【 緑の鳥の子紙を張って 仕上げました!】 | ||
腰張りの紙は 本来 、 白は 「 西の内紙 」 紺は 「 湊紙 」 を使います。
これらの紙は鳥の子紙と違い 厚みが薄く 糊が付いた湿った状態では 綺麗に切ることが出来ません
クロスなら 張った後 柱に沿って 地ベラを当て それに沿ってカッターで切れば 綺麗に仕上がりますが、
腰張りの紙は 湿った状態で 地ベラを当てて切ろうと思えば、引っ掛かって破れてしまいます・・・
腰張りの張り方は、事前に紙を湿らせ 下の写真の様に 柱の方を取って、丸包丁で切ります (^^)/
例えば 上の写真の右側の出っ張ってるところですが、竹を加工していますので 下の方にフシが付いています
 |
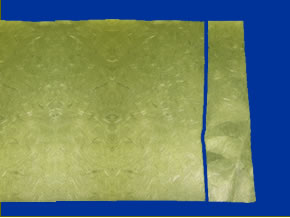 |
|
| 【 竹のフシで形が歪です・・・ 】 | 【 型を取って 包丁で型通りに裁ちます 】 | |
 |
||
| 【 張りつけると 竹のフシの型通りに収まりました (^^♪ 】 | ||
糊を付ける前に 紙を湿してから 竹のフシの型を取って 丸包丁(カッターでは切り難いです・・・)で裁ちます。
そこに糊を付けて、フシに合わせて張りつけて完了です (^^)v
京都で修業をしている時には、お茶室だけでなく 普通の民家・お茶屋さん・料亭 など の腰張りに良く出かけましたが、
最近は 少なくなりましたね! 壁にちょっと張るだけで、純和風の上品な雰囲気を醸し出せます (^^)/
皆さんも如何ですか?
2012/3/11 書く
コメント
 コメントをする
コメントをする

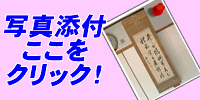
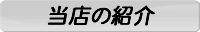


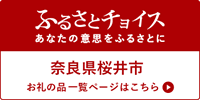



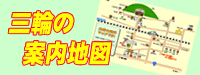


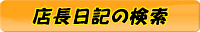


コメントはまだありません。